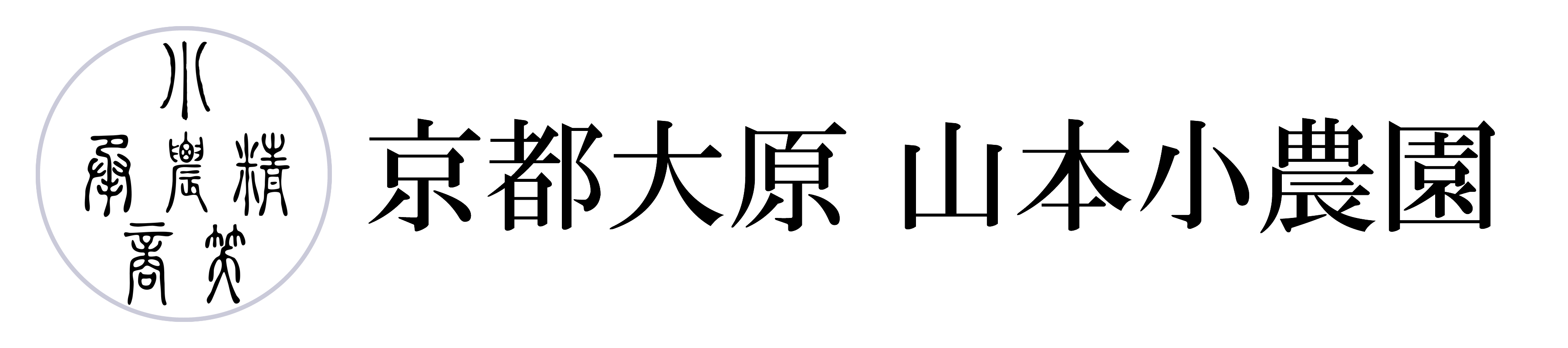地域と農園を豊かで面白くするための小さな挑戦
山本小農園では、普段の農作業と共に、様々な小さくて楽しい挑戦をしています。
これらの、挑戦は最初から意図して行ったものもあれば、農業を続けていく中での偶然の出会いにより始めたものなど様々な物があります。
いずれにせよ、肩ひじ張らずに楽しみながら、またはちょっと野心的にやってみたい物ばかりです。
大原産赤紫蘇の伝統を引き継ぐ

大原の名産品である「しば漬け」の原料として有名な大原の赤紫蘇。
大原の赤紫蘇は、四方を山に囲まれ、他の地域の赤紫蘇と交雑することなく、800年以上繰り返し栽培され続けて来ました。また、赤紫蘇の原種に最も近く、その芳香と色づきの良さは赤紫蘇の最高峰の品質として知られています。
赤紫蘇の種は、他の地域から持って来てもいけないし、出してもいけない。たとえ大原の赤紫蘇の種を他の地域で栽培しても、大原で栽培された赤紫蘇の良さは再現出来ないと言われています。
大原の農家にとっては、赤紫蘇は数ある野菜の中の一つでは無く、大原の農家としての「誇り」を支えるものなのかも知れません。
私たちの農園でも、地元の農家の方に一握りの種を分けて頂いてから、毎年自家採種を繰り返し栽培し続けています。
赤紫蘇の種を渡された時は、「大原の農家として赤紫蘇を絶やさない様に頑張ってくれよ」と言われた気がしました。
これからも、大原の農家である誇りを持ち、大原の赤紫蘇を守り続けて行きます。
地元経済に少しでも貢献する

就農当初の新規就農者にとって、野菜を栽培することが難しいのは当たり前ですが、次に問題となるのはそれをどうやって売るかという事です。
自給自足の農ではなく、農業で食べていくとしたら、栽培と販売は経営の両輪で、どちらが欠けても経営は上手く行きません。
自分にとって運が良かったのが、就農してからすぐに大原の地元の直売所「里の駅大原」がオープンした事でした。
栽培方法が未熟で、まとまった量の生産が無いのにも関わらず、直売所では少数でも出荷でき、現金収入が得られたのです。
就農当初の自分にとって、それは本当に助かるものでした。
逆に、「里の駅大原」や「大原ふれあい朝市」が無かったとしたら、今よりも販売にかなり苦労していたと思います。もしかしたら、最初の数年で廃業していかも知れません。
なので、せっかく大原で農業をやるのだから、「大原のためになる農業をしたい」というのが、これからも変えてはならない山本小農園の大原則です。
具体的にやることは、地元の直売所「里の駅大原」へ出来る限り毎日野菜を出荷し続け、毎週日曜日に開催される「大原ふれあい朝市」に出来る限り毎週出店し続けること。
耕作することによって田畑を守ると同時に、地元にお金を落とし、少しでも地元経済に貢献すること。
これからも、この立ち位置を踏み外すことなく、農業を続けて行こうと思います。もちろん、今後はもっと力を蓄えて、より地元に貢献して行きたいと考えています。
玉虫の森

2020年9月、2度目の大原での生活が始まりました。
ようやくたどり着いた家は、山付き物件で、家の裏側には、鬱蒼とした木々が屋根に覆いか被さり、日当たりを悪くしていました。
このままではいけないと、地元の人に伐採をお願いし、その年の冬にかけて、家の周りの木をある程度切って頂きました。これで、かなり日が差し込むようになり、家の周りの雰囲気ががらりと明るくなりました。
その後も伐採を進めた結果、山は日差しが届き、時折家族で裏山へ登って大原の風景を見渡したり、山頂で簡単なご飯を食べるなど、活用次第で面白い可能性があるものへと変わりました。
さらに、この裏山を活用するにはどうするか?
そんな時に思い浮かんだのが、子供の頃に雑木林でカブトムシやクワガタムシを捕った記憶でした。
さらには、たまに見ることがあった美しいタマムシ。タマムシの事を調べてみると、エノキの木を好むことが分かりました。エノキの木は、他にもオオムラサキも好むことも分かりました。
そこで、裏山をエノキを中心にクヌギなども植え、様々な生き物が集まる場所にすることが決まりました。さらには、林道と階段を作り、頂上まで楽に登れるようにしました。
2024年の春には、試しにエノキやクヌギなどの数本の木を植え、裏山を「タマムシの森」と命名しました。
そして、これからも木を植え続けて行きます。
完成するのは遥か先で、その時には自分は生きてはいないと思いますが、裏山がタマムシやオオムラサキ、カブトムシやクワガタムシなどが棲息する森になると想像するだけで、ワクワクが止まりません。
耕作放棄地をゆず畑に

2022年の冬、地元の方に耕作放棄地を借りてみないかと相談されました。実際に現場を見に行ったところ、畑には向いていないものの、以前は仏前に供えるシキミなどの木が栽培されていたことが分かりました。
何らかの果樹を栽培したいという思いがあったので、果樹を植えて良いならという条件で、お借りしました。
そして、翌年の3月植樹を開始。植え付けたのは、約30本の柚子の木。
大原は冬場に氷点下まで気温が下がるので、耐寒性が強い作物が適してる事と頻繁に鹿が侵入するので、幹にとげが生えている柚子が鹿の害に強いのではないか。また、柚子なら加工品にも向くのではないかという考えからでした。
柚子の実が出来るには、まだまだ時間がかかりますが、気長に待っていこうと思います。
黒プラスチックマルチを使わない栽培

山本小農園では、就農当初から現在まで、農薬や化学肥料を使わず作物を栽培する、いわゆる有機栽培を行っております。2013年には、有機JAS認証を取得しました。
元々有機栽培を始めたのは、農薬や化学肥料の負の側面がクローズアップされた時代の反農薬・化学肥料という方向からのアプローチではなく、漠然と田舎暮らしを楽しみたいというゆるい思いからでした。
その様な浅い考えで、なるべく環境に負荷を与えない有機栽培を始めました。
有機栽培で一番大変なのが雑草対策です。最初は簡単に除去出来るで小さな草も、他の作業の忙しさでしばらく放置しておくと、いつの間にか根がしっかりと張って抜くのも大変になり、やがて畝全体を覆い、肥料を吸い、作物の光合成を阻害します。
就農一年目は、今よりもはるかに狭い耕作面積にも関わらず、夏場は草取りに明け暮れ、本来の必要な作業まで手がまわらずに、良い実りを得ることが出来ませんでした。
さすがにこのままでは経営が危ういと思い、2年目からは雑草防除のために黒プラスチックマルチを使い始め、その便利さの為、年々使用量も増えて行き、黒プラスチックマルチの使用は栽培にとって必須の物となって行きました。
自分の中でモヤモヤしたものを感じながらも、黒プラスチックマルチの使用量も年々増加し、倉庫には使い終えた使用済み黒プラスチックマルチが山のように積み重なって行きました。
「これが、自分のやりたかった農業なのか?」自分の中での疑問は次第に大きくなって行きました。
そして、2024年の春に、自分の心のバランスを保つためにも、プラスチックマルチ削減の決心をしました。
いきなり全廃というのはハードルが高く、まずは、現実的に?黒プラスチックマルチ不使用に切り替えるという方向で頑張ってみることにしました。
気になる周りの反応ですが、家族も農園スタッフもむしろその方が良いとの意見で一致ました。使い終わった黒プラスチックマルチを畑で剥がす作業よりも、草取りに時間をかける方が仕事をやっていて気持ちが良いとの事でした。
どうなるかと思いましたが、スタッフや援農に来てくれた方々のお陰で、草取りになんとか手が回り、夏を乗り切ることが出来ました。
ただ、ちょっと気を許すとたちまち草が畝を覆うので、常に畑に手が回る人員の配置が必要になります。
当然、必然的に生産コストが上がります。
また、黒プラスチックマルチには保温や保湿、病気防止など雑草防除以外の大きな効果もあるので、それが無い分どのように野菜の生育を順調に保つかなど、まだまだ課題があります。
いずれにせよ、とにかく続けてみる事。まだまだ、手探りですが、数年以内に黒プラスチックマルチを使わなくても畑がまわって行き、作物も健全に育つ栽培方法を確立したいと意気込んでいます。
なお、これはあくまでの自分の中での決意であり、他の人の農法に対して何か言うつもりや他人に勧めるつもりも一切ありません。