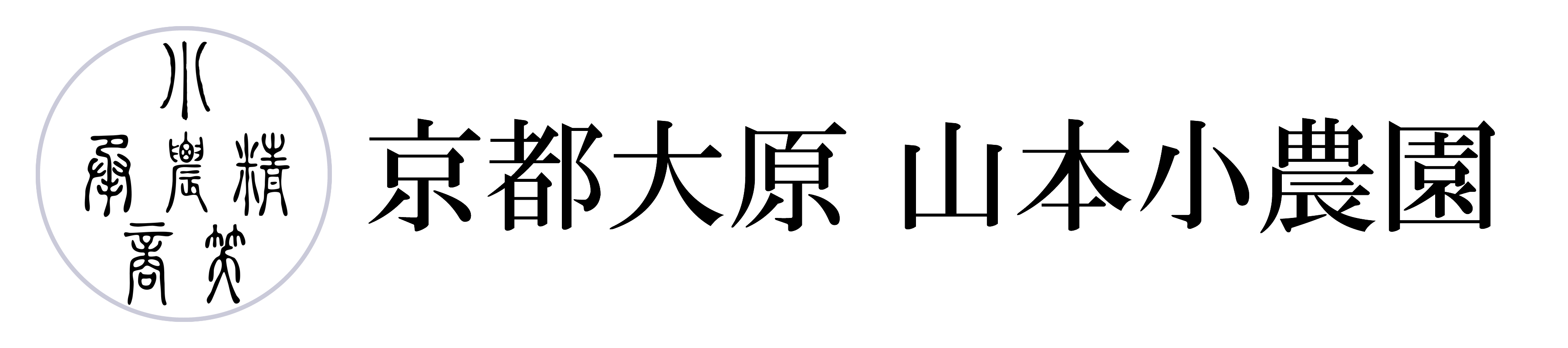栽培方法総論
山本小農園の野菜作りについての、総論的な栽培方法です。総論なので、栽培についての具体的なことではなく、あくまでも心構えという側面にクローズアップしました。
具体的な栽培方法や栽培状況については、それぞれの野菜ごとに、今後、別途述べさせて頂きます。
栽培上の立ち位置について
山本小農園では、有機農業を行っていますが、食料安全保障の観点から言えば、有機農業を「無暗に」拡大する必要は無いと思います(産業としてではなく、自給自足や生きがいとしての有機栽培、自然栽培は、どんどん広がって行けば良いと思います)。
なぜならば、性急に不慣れな有機農業を拡大することにより、害虫や病気が多発し、野菜の収穫量が減り、国民が飢える危険性すらあるからです。外国から安価に食料を輸入するのも、今後の国際情勢では無理があると思います。
したがって、まずは、問題点は修正しつつ、現行の一般的な農業により国民に十分な食料が行きわたることが、何より必要であると思います。
その上で、それだけでは拾い切れないニーズ、例えば健康志向や環境保全などを有機農業で拾い上げて行くべきです。
つまり、同じ農業でも慣行農業と有機農業とは全く違う土俵にあり、お互いの役割があり、お互いがそれぞれの役割を自覚し、相互補完しながら国を豊かにしていくものであると思います。
以前に比べると有機農法への理解も広がりました。これは、ひとえに先輩農家や運動に携わった方々のお陰であります。一方、有機農法の意味合いも、有機第一世代の反農薬運動という側面からはかなり変容して来ました。
有機と言っても解釈は様々で、広くライフスタイルを意味する有機・オーガニックから狭義の農法を意味する有機まで様々です。
私は、ライフスタイルとしての農業に憧れ、その延長線上で有機農法を始めました。実際にやってみると、泥臭いものですが。
ただ、新規就農から有機農業を続けていく中で、自分の中で有機栽培があまりにも当たり前になり、ことさら有機農業であることを主張する意欲も無くなりました。
有機と慣行、さらには、自然農法など区別して優劣を争う程の事でも無いように思います。
聞かれれば、一応有機農法と答えますし、野菜にも有機JASマークを表示することも多くありますが、自分の中ではあまり重要ではありません。
自分にとっての農業は、有機農法・有機農業という言葉が生まれる以前の、特に区別も無い、自分にとって当たり前の営みなのです。
農法よりも、毎日、朝になったら、畑に出て土を耕し、草を取り、水をやり、日が暮れたら家に戻り、ご飯を食べて、眠る。もちろん、現金収入を得るためには、バリバリと畑仕事をこなし、出荷作業もかなり頑張る。
そうこうしている内に、いつの間にか年をとる。そんな、生活の中にある有りのままの農業でありたいと思います。
農薬と化学肥料について
栽培においては、農薬や化学肥料は使っておりませんが、そもそも、農薬や化学肥料を使う必要が無いことを理想としています。
そのためには、病害虫が発生しにくい状況を作りださなければなりません。また、少々発生しても作物自体がそれらに負けないような力を持つことが必要で、その為には健全な土づくりが必要です。そして、健全な土づくりをするために適切な有機質肥料の使用が必要です。
有機質肥料は、土壌に棲息する微生物の餌という位置づけをしています。
人間の腸と畑の土壌はよく似た関係で、腸内細菌が健全で腸内環境が良ければ人間も健康になりますし、畑の土壌微生物が健全であれば、そこで育つ野菜も健康に育ちます。どれだけバランスのとれた微生物の世界が出来るかです。
また、有機質肥料は、微生物の分解作用を経て野菜に吸収されるので、化学肥料に比べてゆっくりと効きます。急激に栄養を吸収した場合は、植物体内の栄養のバランスが崩れる事がありますが、ゆっくりと無理なく肥料分が吸収されることにより、野菜も無理なく育ちます。
具体的には、土づくりには、粗大有機物の補給として、前作残渣や雑草のすきこみや近くの製粉業者から頂けるそば殻やクズそばを用います。元肥は米ぬかを中心とし、カルシウム分の補給が必要な時には牡蠣殻石灰を用います。追肥には有機JASでも認められている鶏糞を使用します。土に投入するのは、これだけです。
以前はぼかし肥えなどを自分で作っていましたが、今ではそば殻や米ぬかを投入すると畑の土壌微生物の働きでやがて自然に発酵するので、わざわざ作る必要も無いと思い作っていません。また、今後は、緑肥の活用をもっと図っていきたいと思います。
今行っている栽培方法も、工夫の中から考えついたもので、今後も色々な考えを取り入れて変わって行きます。技術の進歩にはキリがありません。常に向上心を持って励んで行きます。
連作障害を避けるための作付計画
土台の技術としての土づくりと共に、輪作を心掛けています。
同じ作物を同じ畑で栽培すると土壌微生物やミネラルが偏って来るので、病害虫の被害を受けやすくなります。いわゆる連作障害です。
連作障害を避けるには、同じ作物を連続して作付けしない輪作が必要になります。
ただし、これは野菜の種類ごとの連作を極端に嫌うものや連作しても問題の無いもの、その中間の物など、多岐に渡ります。
その多岐に渡る野菜を畑の条件、種まき、植え付け、収穫時期、水のやりやすさ、過去の作付けなどの条件を考慮しながら毎年、作付け計画を立てます。
畑が皆同じ四角形で、水はけが適切で、石もなく、獣害が無く、水回りがよく、機械も入れやすいなら、作付け計画を立てるのは楽なのですが、畑はいろいろな条件があり、その条件を組み合わせなければならないので、作付け計画はまるでパズルゲームをやっているようです。
また、キャベツやブロッコリーなど真夏に育苗しなければならない作物については、農薬を使わず、なるべく資材を使いたくないので、作付け計画から外さざるを得ないという場合もあります。
もちろん、一度計画しても想定外の事だらけなので、その都度、その状況の最適解になるように変更することは多々あります。
また、作付け計画と共に、毎日の栽培記録が必要になります。
いつ、どの畑で、どんな作物を、どのように栽培したか。播種間隔や植え付け間隔、間引き、追肥の記録など、毎日畑から家に帰ったら、記入することが必要です。これが、来年の作付け計画にも反映されます。
作付け計画を実際の畑に落とし込み、それを記録し、その結果を検証して、来年の作付けに生かす、一連の流れを意識して栽培しています。
適切な時期の適切な管理
計画が出来ると、いよいよ畑を整え、種まきや植え付けを行い、草取りや追肥、支柱立て、誘引などの管理を行います。
その時に必要なのは、まず必要な作業を行える技術を持つこと。
例えば、種まきは播種機を使って行いますが、播種機も種を播く間隔や深さなどを作物の生育過程と完成形をイメージしながら適切な設定で播きます。植え付けも、光の当たり具合、病害虫の被害遭わないにどうするか、どれくらいの収穫量を得たいのかなど。草取りも、手で取るのか、クワで取るのか、また、クワで取る場合にはどのようなクワの使い方が良いのか、などなど。
そして、重要なのが、適切なタイミングを逃さないこと。
いくら技術があっても、タイミングを逃してしまうと、大失敗へまっしぐらです。
例えば、除草にかんしても、最初は見えるか見えない位だった雑草も、他の作業に手を取られているうちに、みるみる大きくなり、除草するための労力が何倍にもかかり、最悪その野菜をあきらめなければならない場合もあります。
追肥も、作物がこれからぐんぐん肥料を吸うという時期に分解も考慮してきちんと施すことが出来るか。もちろん、夏野菜で作物の生育に支柱やネットの仕立てが間に合わなければ、まともな収穫は期待出来ません。
野菜作りの上手い下手は、実は、この管理能力が8割を占めていると言っても過言ではありません。
それには、自分で場当たり的に全てを何とかしようとするのではなく、段取り能力や組織の管理能力も必要になります。
一見華やかなファインプレーを褒め称えるのではなく、ファインプレーをしなくても良いような余裕を持つようにしたいと思います。
新しい挑戦
2024年からは、新しい挑戦として黒プラスチックマルチを使わない栽培に挑戦しています。
ただ、黒プラスチックマルチを使わないだけでは、除草のための労力が大幅にかかったり、土が乾燥に晒されるなど、栽培上難しい点があることは否定出来ません。なので、ただ単に黒プラスチックマルチを使わないだけでは、積極的な効果の無い単なる窮屈な農法になってしまいます。
従って、これからは黒プラスチックマルチ不使用と新たな技術を組み合わせて、無理なく、また、黒プラスチックマルチを使っていた時には無かったようなメリットのある農法を確立しなければなりません。
そのための方法として、例えば、畝間の活用を考えています。畝間で緑肥や雑草を活用することにより、畑の中に小さな生態系を再現して病害虫の多発を抑えたり、肥料分を供給するなどの新しい技術と考え方を取り入れて、試行錯誤して、技術を一歩でも前進させたいと考えています。
成功するか失敗するかは分かりませんが、経過については、随時報告させていただきます。
栽培方法各論
山本小農園で栽培している野菜は、全て露地野菜で年間30~40品目あります。それぞれの野菜の栽培方法については、まだ写真が無いので、これから順次栽培するごとに写真と共に栽培方法もアップして行きます。